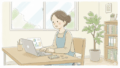「就労継続支援B型事業所の職員ってどんな仕事をしているの?」
「資格や経験がなくても働ける?現場はどんな感じ?」
福祉の仕事に興味があっても、イメージがわかなくて不安…という方は多いと思います。
私は地方在住の40代アラフィフ、子育てをしながら『就労支援B型事業所の職員』として働いています。
資格なし・未経験・コミュ力にも自信なし…という状態でこの仕事を始めましたが、数ヶ月で慣れ、今も楽しく居心地よく続けられています(^^)
この記事では、現役職員の立場から「就労B型の職員の仕事」についてリアルにお伝えします。
未経験から挑戦したい人や、自分に向いているか知りたい人、働きやすい職場を探しているワーママの参考になればうれしいです!
就労支援B型職員の仕事は、障がい者さんの「働く」をサポートすること

就労継続支援B型事業所は、障がいのある方が「働く場、働く練習をする場」として通う福祉サービスです。
一般企業での就労が難しい方に対して、事業所が仕事の場を提供し、作業や活動を通して「働くリズム」や「生活の安定」を支えています。
地域や事業所によって特徴はさまざまですが、就労B型の『利用者さん』の主な作業内容には次のようなものがあります。
- 室内作業(袋詰め、箱折りなど内職の仕事)
- 外作業(清掃業務、軽作業など請負の仕事)
- 農作業や家庭菜園
- PC作業やクラフトなど事業所独自の取り組み
利用者さんたちは、こういった生産活動で得られた売上を『工賃』として受け取っています。
そして、就労支援で働く職員は「生活支援員」や「職業指導員」と呼ばれ、利用者さんが安心して働けるようにサポートするのが仕事となります。
職員の給料は、障害福祉サービス報酬(国からの補助金)から支払われます。
▼就労B型職員のリアルな給料&ボーナス実例はこちら!
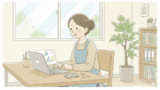
就労支援では、利用者さんは作業を通じて働き、職員は利用者を支援することで働く。
利用者さんは、介護を受ける人でもお客様でもありません。
『お互いに働く人同士』が働く場というのが、就労継続支援ならではの特徴だと思います。
就労支援B型の現場ってどんな感じ?→びっくりするほど『普通』でした!
私自身は就労B型で働く前に、障がい者さんと接することがあまりありませんでした。
就労支援という言葉は知っていても、
- 現場はどんな感じなのか?
- 利用者さんの心身の状態は?
- 職員はどの程度の支援をするのか?
実際に働き始めるまで、まったくイメージがつかなかったんです。
ですので、何を見ても大丈夫なように「すごく混乱していて大変で壮絶な現場」を想像して心構えをしてました。(根がネガティブなんです)
でも、勤務初日に、恐る恐る事業所のドアを開けたら ーー
「なんと落ち着いて静かな職場なんだ…!」と逆にびっくり(笑)
ひとこと障がいと言っても、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害とさまざまで、利用者さんの心身の状態や必要なサポートは一人ひとり違います。
問題なくコミュニケーションを取れる方や、外見からでは『普通』にしか見えない人もたくさんいます。
なにより、就労継続支援に通う利用者さんは「働くために」通所されているので、ある程度、自立して動ける方が多いのです。
職員が手取り足取りサポートしたり、なんでも介助が必要なわけじゃない、と知ってホッとしました。
むしろ、利用者さんの自立支援のために、職員は手を出しすぎないことも大事な姿勢になるんですよ。
なんだか子育てに似ていますね。
就労継続支援B型職員の主な仕事内容【向いているのはこんな人】

では、就労B型の『職員』は、どのような仕事をしているでしょう。
事業所によって様々ですが、現役職員の目線をまじえて、一般的な仕事の例と向いている人の例をあげてみますね!
① 作業のサポート(補助・検品・見守り)
利用者さんが行う作業の手順を説明したり、困っているときに手助けしたりします。
- 室内作業では、手順を教えたり、仕上がりを検品したり。
- 外作業では、一緒に作業しながら見守りや声かけをします。
手先が器用で穏やかに対応できる人は、職場として活躍できること間違いなしです(^^)
また、仕事中は静かに作業することが多いです。
落ち着いた環境で働きたい人や、あまりおしゃべりせずに黙々と過ごしたい人など、内向的な人は就労B型の職員に向いていると感じます。
② 送迎業務(車の運転)
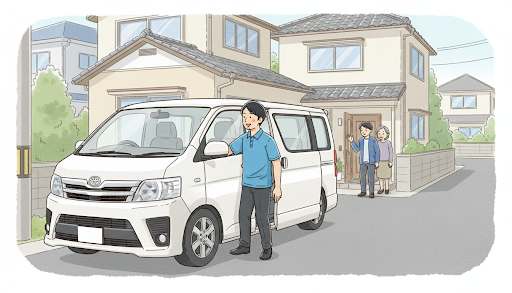
利用者さんをご自宅や駅まで車で送り迎えするのも、職員の仕事のひとつです。安全運転と時間管理が求められます。
事業所の規模によって、社有車のサイズや車種はさまざま。
うちの事業所では、軽自動車、普通車、ミニバン、福祉車両など、送迎ルートによって使い分けていますよ。
地方では、職員による車での送迎業務は必須で、大きなウエイトを占めます。
このため、B型事業所職員の求人に応募すると、
- 運転免許は持っていますか?
- 普段は運転をしていますか?
- 家でどのような車種を運転していますか?
など面接で確認されたりします。
ちなみに、私は就労B型の仕事を始める前、運転は嫌いじゃないけど得意ではない位のレベル。
子供のお友達を乗せて運転するのはできるだけ避けたいと思ってきましたし、いわゆるミニバン(家族向けの大きな車)を運転したこともありませんでした。
ですから、就労B型の職員になってからは、人を乗せて運転するプレッシャーですごく緊張しました…(>_<)
知らない道や細い路地をミニバンで走る毎日はドキドキの連続。
でも、毎日運転するうちに、技術も地図感覚も自然と身について、今では安心して運転できています。
車の運転に自信がない人ほど、丁寧で慎重な運転ができるものです。
自分の運転で人を乗せるのが不安だと感じる人ほど、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。
▼送迎の仕事内容や大変さは、こちらで詳しくお話ししています

③ 生活支援
「今日は元気ないな」「どうも体調が悪そう」など、利用者さんの小さな変化に気づくのも、職員の大切な役割です。
そっと話しかけたり、別室でお話を聞くこともありますよ。事業所では静かでも、送迎中ならおしゃべりに花を咲かせる利用者さんもいます。
利用者さんの話を遮らず、丁寧に耳を傾ける姿勢は、就労支援の職員に必要不可欠です。
もし、異変や体調不良に気付いたときは、事業所にいる「サービス管理責任者(通称:サビ管)」などに報告し、対応します。
また、利用者さんの身体状況によっては、車椅子の補助やトイレ介助を行うこともあります。
介護の経験や資格がなくても大丈夫です。
その人その人に応じた介助が必要になるため、身体の支え方や操作方法など、先輩やサビ管などから事前にレクチャーを受けますので、安心して現場に入れます。
④ 事務・書類作成
福祉の仕事は「書類」が多いのも特徴。
利用者さんの出欠や勤務時間、作業内容の記録、行政への報告書などを作成します。
最近はPCやクラウドを導入する事業所も増えているため、事務仕事の経験やパソコンスキルがある人は重宝されます。
私も、以前は自宅でフリーランスとして働いていてパソコンやITはそれなりに使いこなせるので、今の職場では頼られることが多いです。
エクセルやワードはもちろん、新しいツールの選定や導入・設定、運用方法の構築なども任せてもらえるので、やりがいがありますし面白いですね(^^)
▼就労B型職員の1日の流れの例はこちらをどうぞ!

補足:農業、カフェ、PC系… 就労B型にもいろんな働き方がある

ちなみに、「就労継続支援B型」ってひと口に言っても、やってることは事業所ごとにけっこう違います。
たとえば、専門的なことに取り組んでいるところだと、
- カフェ・製菓系:お店を開いたり、イベントでパンやお菓子を販売したり
- 農業系:農家さんと一緒に作業したり、自分たちの畑で野菜や花を育てたり
- PC・クリエイティブ系:データ入力やチラシ作り、HP更新、動画編集やイラスト制作なんかをやっていたり
こんなふうに「その事業所ならでは」の仕事があるんです。
一方で、一般的なB型事業所では、
- 室内でできる軽作業や内職
- 公共施設や会社の清掃といった外作業
といった、地域の企業や工場からの下請け作業がメインになっていることが多いです。
うちの職場も、後者の一般的なスタイルですね。
だから、同じ「B型」と言っても、職員の働き方や求められるスキルは、事業所のカラーによってけっこう違いますし、
就労継続支援A型や就労移行支援では、職場の雰囲気や仕事への取り組み方が、もっと変わってきます。
必ずしも、業種や職種だけでは、自分に合うかどうかは判断できない、ということです。
求人を探すときは、自分の得意・苦手を整理して、過去の仕事で嫌だったことや転職理由を振り返ると、
『長く働ける職場』に出会いやすくなりますよ。
▼『自分の性分に合う職場』を引き寄せる具体的方法は、こちらでお話ししました。
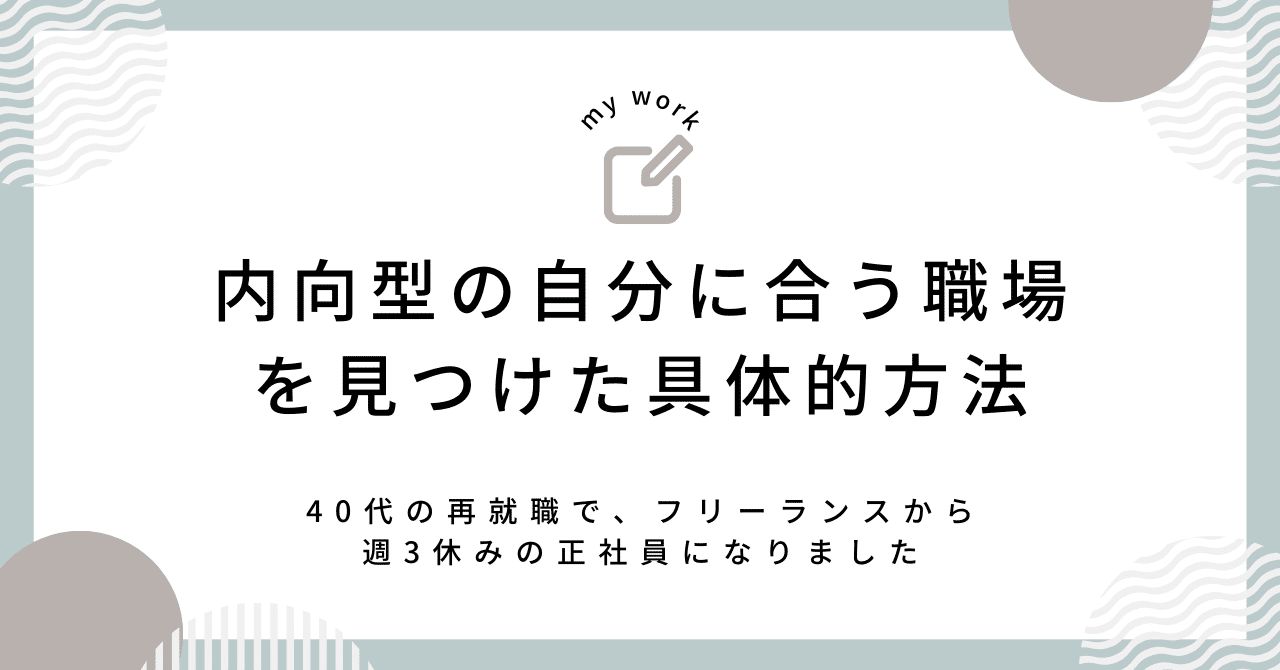
現役職員から見た、就労支援B型の職員に求められる『資質や人物像』は?

就労支援B型の職員にいちばん大事なのは、
利用者さんの「その人らしさ」を理解して寄り添うことだと思います。
もちろん思い通りにいかないことも多いので、
予定変更やハプニングがあっても、「まあ、そういう日もあるよね」と、気持ちを切り替えられる柔軟さが必要です。
逆に、切り替えができないと、
「なんでできないの?」「ちゃんとしてよ!」とイライラしてしまいますし、
利用者さんとの関係もうまくいきません。
自分の機嫌は自分でとれないと、周りのスタッフがフォローで疲れてしまうことも…。
どうしてもイライラをコントロールできなくて辛い人は、こちらを読んでみてください。

就労B型職員の仕事のやりがいや喜びはる
- 利用者さんの小さな成長や挑戦する様子を近くでゆっくり見届けられること
- 「話を聞いてもらえて楽になった」と利用者さんの安心した表情を見たとき
- 送迎や納期、イレギュラーな対応に追われて忙しいときの集中力と充実感
- 作業の流れや工程を見直したり工夫したり、改善の余地がたくさんあって楽しい!
日々の中で「誰かの役に立っている」「自分も少しずつ成長してる」という実感を得やすい仕事だなと思います。
就労B型職員の仕事で大変なところは?
もちろん、良いことばかりではありません。
- 送迎は「安全運転+時間厳守」のプレッシャーあり
- 利用者さんの体調や気分で予定が変わり振り回されることも多い
- 書類仕事が意外に多いので、文章を書くのが苦手だと負担に感じる人も
- 柔軟な対応力や忍耐力が求められる
「人と関わる仕事」なので、完璧を求めすぎるとしんどい場面が出やすくなるかもしれません。
「そういうときもあるよね、仕方なかったよね」って、利用者さんにはもちろん、周りのスタッフや自分にも優しくできると良いですね(^^)
▼40代福祉未経験で就労B型職員になった私が、大変だったこと・失敗談はこちら!

就労継続支援B型とA型の違いは?職員として働きやすいのはどっち?

なお、就労継続支援には「A型とB型」があります。
どっちの方が働きやすいか、自分に向いているか知りたい人もいると思いますので、職員目線で比較してみますね。
まず、A型とB型との違いは「雇用契約の有無」です。
A型では、利用者さんは事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給料をもらって働きます。
そのため「仕事」としての責任が強く、職員も効率や成果を意識して一緒に働きます。
B型は、雇用契約は結ばず、工賃を受け取りながら、比較的自由なペースで通えます。
体調に波がある方や、短時間しか働けない方も利用できる仕組みなので、職員には柔軟な対応が求められます。
一見すると「B型の方がゆるいのかな?」と思われがちですが、職員目線で見ると、そうとも言えません。
というのも、B型で働く利用者さんたちは、自立して動ける方ではあるものの、何かと手のかかる方も多いのです(身体的、精神的、性格的な面などにおいて)。
その人その人に応じた配慮や手助けが必要なので、職員は細かな対応やイレギュラーに追われ忙しかったりもするんです。
つまり、A型=効率重視、B型=柔軟対応重視 というのが職員目線での違いです。
✅ まとめると…
- A型=効率重視(決まった仕事をバリバリやりたい人向き)
- B型=柔軟対応重視(イレギュラーも柔軟にこなしたい人向き)
と言えますね。
▼就労支援B型とA型の服装の違いはこちらをどうぞ!

就労支援のカラーは、地域や事業所による違いも大きい
また、同じB型事業所でも、方針や規模によって雰囲気はかなり異なります。
就労支援の仕事に転職を検討している人は、ざっくりと違いを知っておくと良いでしょう。
工賃重視の事業所
ノルマや納期があるので、職員も作業量が多くて、(サービス)残業もあるかも…
知的障害の方が多い事業所
単純作業が中心で同じ作業をひたすら繰り返す毎日かも…
精神障害の方が多い事業所
急な体調不良やメンタル異変が起きやすく、細やかな配慮や突発的な対応が必要なので、職員はバタバタ忙しいかも…
事業所によって目指す方向性はさまざまですし、職員の働き方や待遇・お給料も変わってきます。
そして、「働きやすい職場」かどうかは、自分の性格やこれまでの働き方を振り返ることで、見えてくるものだと思います。
求人を探すときは、勤務条件はもちろん「どんな方向性の会社なのか?」「自分はどう関わりたいか」をイメージしてみましょう。
ホームページやSNSの発信をチェックしたり、面接で直接お話を聞くことで、「何を大切にしている事業所なのか?」が見えてきますし、自分に合う職場が見つかりやすくなりますよ。
まとめ
「福祉の仕事に興味はあるけど、未経験で大丈夫かな…」という方にとって、就労支援B型は入りやすく、やりがいも感じられる現場です。
私自身、資格も経験もないアラフィフから始めて、今も楽しく続けられています。
周りの職員も40代の未経験から始めた人が多くて、「未経験からでも安心して挑戦できる仕事」だと実感しています。
就労継続支援B型職員の仕事は「送迎・作業サポート・生活支援・事務」が柱になります。
事業所ごとにカラーが異なるので、自分に合う環境をイメージして選ぶのが大切です。