保育園に子どもを預けるようになると、親の目が届かないところでトラブルが起こるケースも増えます。
たとえば、子どもが怪我をして帰ってきたり、いつもと違う様子が見られると
どんな状況で怪我をしたのか、お友達や先生と何かあったのか
親としてはとても心配になってしまいますよね。
そんなときこそ、保育園の先生とのコミュニケーションが大切です。
しかし、時には報告漏れがあったり、詳細な説明をしてもらえなかったりして
さらに不安な気持ちになってしまうこともあります。
もちろん保育士も人間ですから、たまにそういうことが起こってしまうことは理解できます。
ただ、あまりにも頻繁にトラブルや報告漏れが起こるようであれば、
保育園の体制や先生の伝え方に苦情・クレームを言う必要があるかもしれません。
保育園にやんわりとクレームを伝えたいときには、どんな方法があるでしょうか。
ひとつの手段は、「保育園の連絡帳」に書くことです。
相手を目の前にして話をすることが苦手な人でも、
冷静な気持ちで伝えることができます。
このとき大切なのは、感情的にならないように自身をコントロールすることです。
まず日頃の保育に対する感謝を伝え、
起こった事実を淡々と書くようにしましょう。
そこで今回は
【例文】保育園の連絡帳トラブル時の書き方
連絡帳で解決しない時はどうしたら?誰に言う?
クレームだけで終わらせない「その後の対応」を進めてもらうコツ
についてお話します。
【例文】保育園の連絡帳トラブル時の書き方

まずは、保育園の連絡帳でトラブルや苦情を伝えたい時の例文をご紹介します。
要求ではなく「相談」や「お願い」ベースで書くことが、
やんわりとクレームを伝えるときには効果的です。
書き方が心配な人は、連絡帳とは別の用紙に「言いたいこと・伝えたいこと」を書き出してみましょう。
事実と感情を整理して分ける作業(客観的に見る)をしてから連絡帳に書くようにすると安心です。
【連絡帳で解決しない】保育園のクレームどこに誰に言う?先生→園長→役所の保育園課

保育園で子供に起こったことを知りたい時や苦情を申し出た時に、
連絡帳で伝えるだけでは解決には至らないこともあります。
そもそも、怪我やトラブルなどの重要な事項は、連絡帳には書かないようにしている保育園も多いです。
文章で細かいニュアンスを伝えることは難しく、トラブルを大きくしてしまったり、
新たなクレームを生んでしまったりするリスクがあるからです。
そのため、トラブル事例については必ず口頭で伝えるように、先生方を指導している保育園もあります。
その場合、保護者から保育園へ
連絡帳に苦情を書いて伝えたとしても、
求めるような回答や対応をしてもらえない可能性もあります。
そういった事態を防ぐためには、
やはり顔を合わせて伝えることが有効です。
連絡帳で伝えたときと同じように、
感情的にならないように意識しながら
事実とお願いしたいことをシンプルに伝えましょう。
保育園のトラブル「匿名」で相談できる?先生・園長・役所の保育園課・第三者委員会
担任の先生に伝えても、解決が難しそうなときは、
園長に直接相談するというのもひとつの手段でしょう。
このとき「匿名で相談したい」と園長に相談することは要注意。
結局園長から相談した人の名前が漏れてしまい、
かえって気まずくなってしまった…ということもあるようです。
公立の保育園であれば役所の保育課や福祉課に匿名で伝えることで、対応してもらえることもあります。
また、第三者委員会に相談を持ち掛けることも検討してみましょう。
第三者委員会は、保育園外部の人で構成される苦情解決の「社会性」や「客観性」を保つための組織で、詳しくは社会福祉法第八二条に規定されています。
ホームページや園の掲示板などに第三者委員会の連絡先が記載されているところであれば、そこから問い合わせできます。
やんわり保育園にクレーム「その後の対応・対策を知りたい」と伝えておく
保育園にやんわりクレームを入れたその後、
どのように対応してもらえるのかは、とても気になるところですよね。
クレームを伝えたときに、
など、今後の対応をどのようにするつもりなのかを知りたいということを
明確に伝えるようにしましょう。
「わかりました」「申し訳ございません」で
話が終わってしまうことを防ぐことができます。
特に、役所や第三者委員会を通してクレームを伝えたときには
その後の報告がほしいことを伝えておきましょう。
保育士の先生方や園長に直接相談をしたときには、
お礼の言葉と合わせてどのような対応をしているのかを聞くことができるかと思いますが
第三者を通している場合は経過を追いきれなくなってしまうこともあります。
まとめ
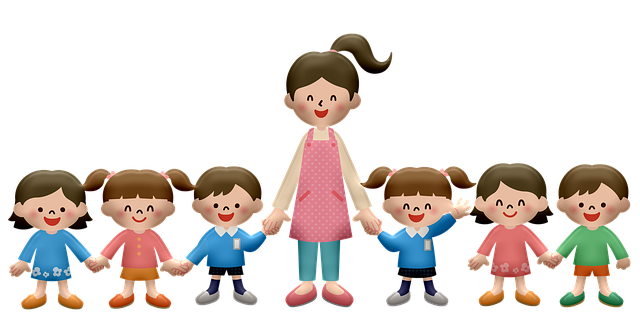
「クレーマーやモンスターペアレントだと思われたら恥ずかしいし…」
という気持ちが、行動を億劫にさせてしまうこともあるかと思います。
今後の関係性を考えてあえて言わない方がいいのか、悩ましいところです。
とはいえ、さらに重大な事態になってしまう前に、心配なことをきちんと伝えることは大切なことです。
保育園にやんわりとクレームを伝えるときに大切なことは、
- 要求ではなく「相談」「お願い」ベースで伝えること
- 感情的にならないよう、事実を淡々と伝えること
- その後の対応を知りたいことを明確に伝えること
です。
親も保育士も、子どもたちが安全に楽しく保育園生活を送れることを目指しています。
コミュニケーションを取りながら、よい関係性を続けていきたいものですよね。
一方的に感情をぶつけてしまっては、いい関係を築くことはできません。
もちろん、我慢して鬱憤をためてしまうことも子どものためにはなりません。
冷静に状況を整理しながら、相談をするようにしましょう。


「今後どのように対応(対策)することを検討されているか、後日教えていただけますか?」